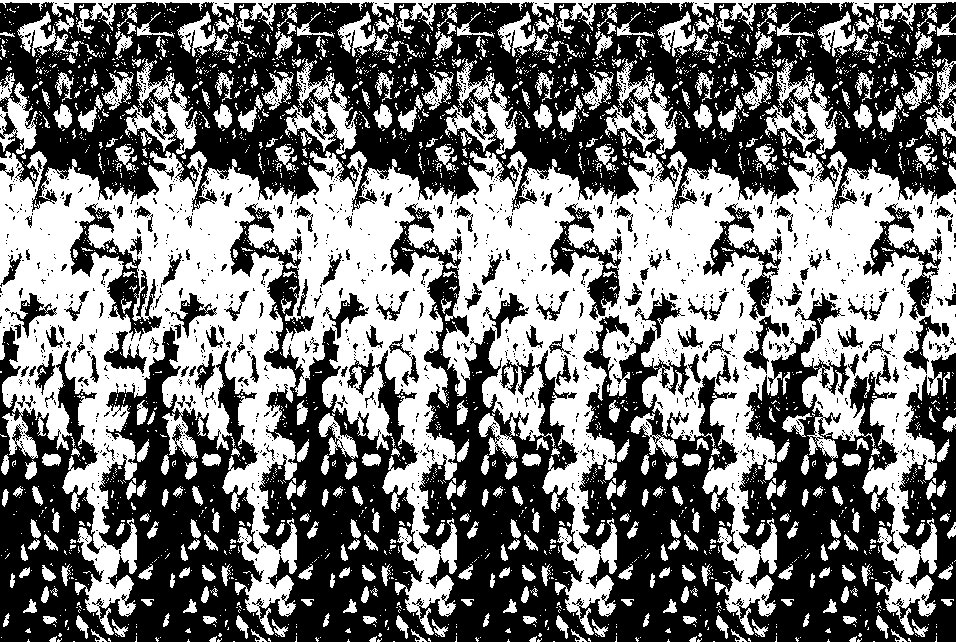|
1
(中略) 秋の都大会では決勝まで進み、延長戦でも決着がつかなかったのでペナルティーキック合戦にまでもつれこみ、結局準優勝に 4冬に例年にない 6 「退部します。お世話になりました」 すでに練習が始まっている校庭の 8「 浅野は首にかけたホイッスルをタバコでもすうように口にくわえた。よく 「本気です。辞めさせて下さい」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
|
9チームメイトたちが 「ああやって 0浅野は 「自分の生き方を自分で決めただけです」 青く高い夏空の下で、中学三年の 浅野は手にした大輪のひまわりを 右ウイングの自分が 学校の花形クラブであるサッカー部の三年生の大量退部は職員会議の話題にもなったようだが、理由が受験勉強に専念したい、という 一学期の終業式を終えて校門を出るところで、 「おれはさあ、頭もよくねえし、板前にでもなっておふくろの店手伝うしかねえんだけど、サッカーやりてえんだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | ||
|
スレート屋根の下の 「都大会のベストイレブンになれたら、私立高校のサッカー部に特待生で入れるかと思ってな。おれはさあ、そう思ってサッカーやってきたんだ。板前になる前にサッカーで花 「悪いな」 「いや、いいんだ。ただ、おれのグチも聞いてもらいたくてさ。気にすんな。おまえ、いいウイングだったよ」 ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | ||
□□□□□□□□□□□□□□