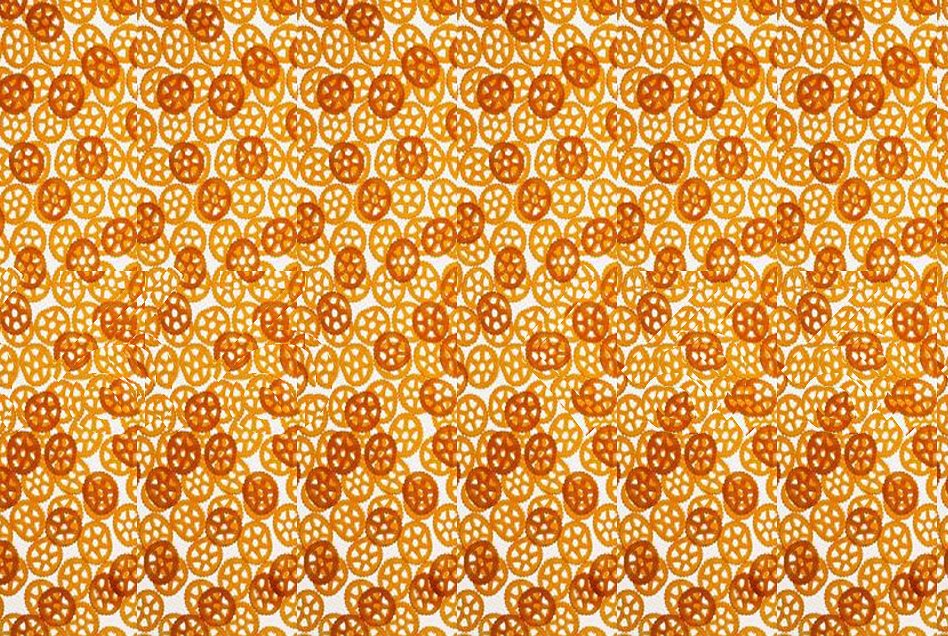|
1本とはふしぎな王国だ。そこにはこの世のあらゆるものごとが生きながらにとじこめられている。
本たちはおとなしい。白い紙の上につつましくくりひろげられた黒い文字の織りなすレース。2そのとばりのかげに数々の 3ときどきふっと、こんなふうに思うことがある。字というものをおぼえてこのかたこの年までに、本のなかで出会った人々の数ははたしてどれくらいだろうか、と。何百人、いや何千人にも 5現実の人間がそうであるように、本のなかの人々も、会ったひとすべてがそのまま友達になれるわけではない。会うそばからわすれてしまうこともあり、目のまえをただ通りすぎていっただけでそれっきり思い出さない場合もあるだろう。 6それでも、長年のうちには、そうした本のなかの住人のいく人かと、生身の友人にもまさるとも 7本がもたらしてくれた友人は、何も作中人物ばかりとはかぎらない。たいていの本にはその生みの親である作者がいて、その人々との交流もまた楽しいものだ。8作品自体はそれほど成功していなくても、また文学書以外の実用書や科学書でも、それを書かずにいられなかった作者や 9本のなかの (矢川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
□□□□□□□□□□□□□□